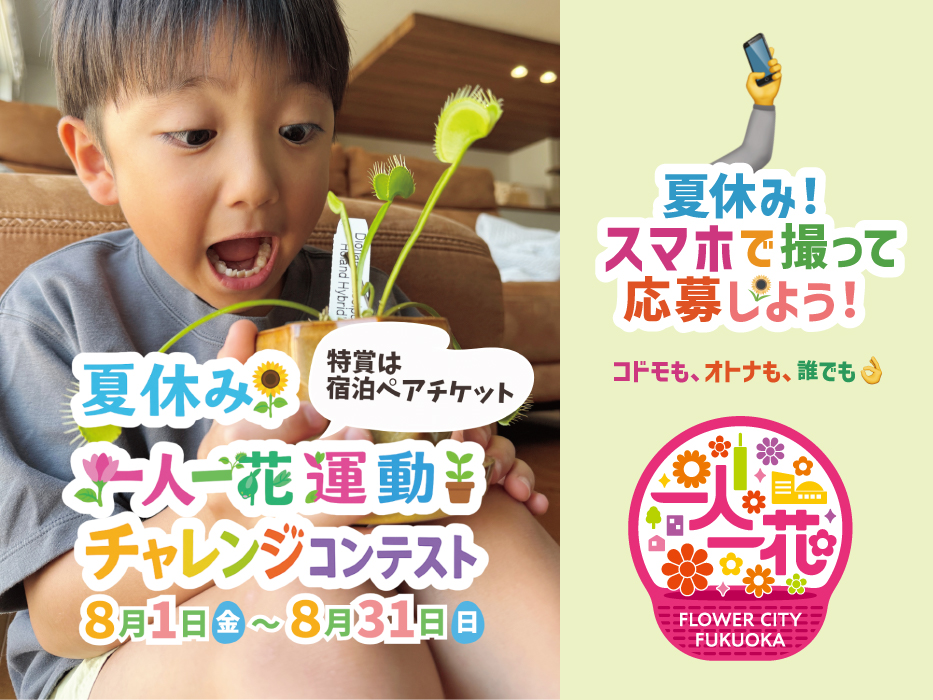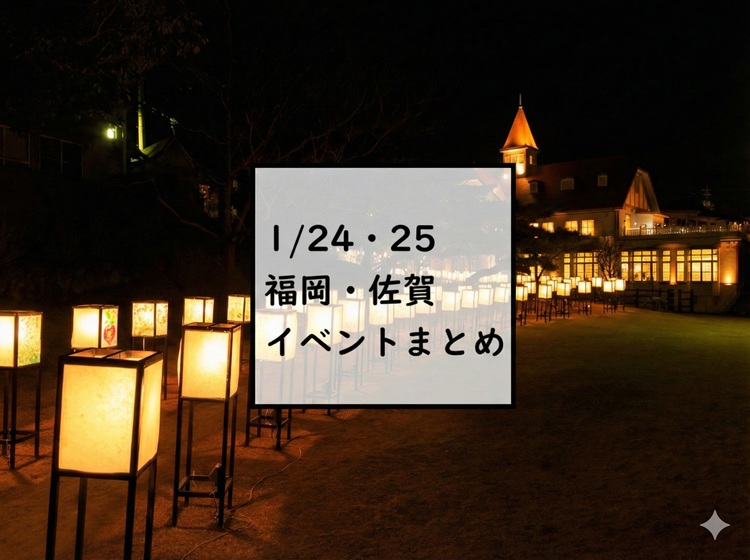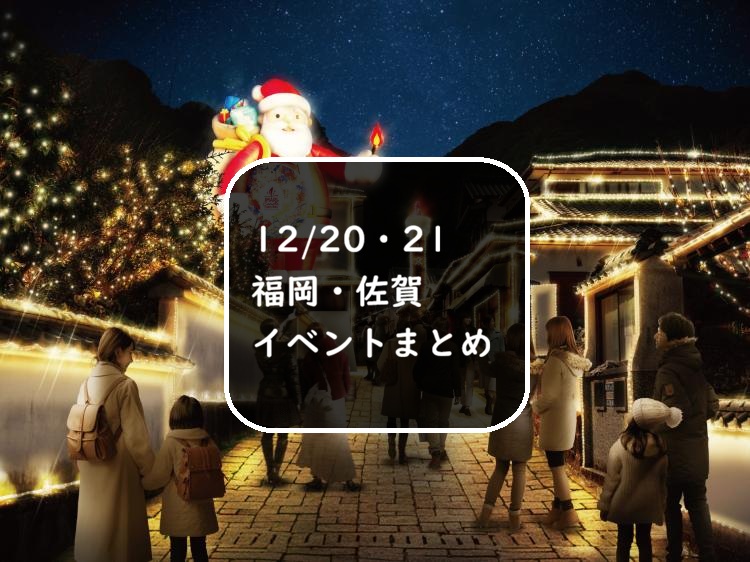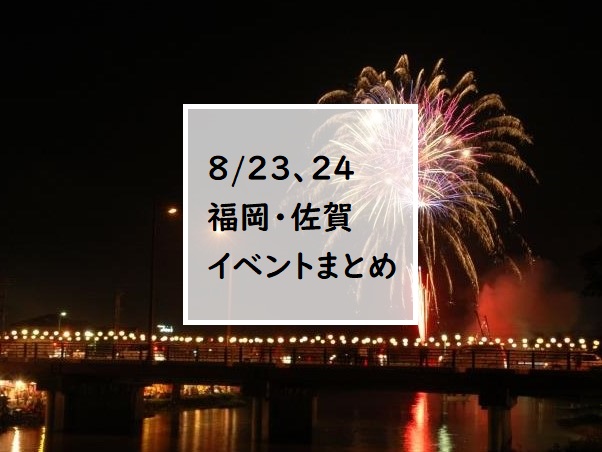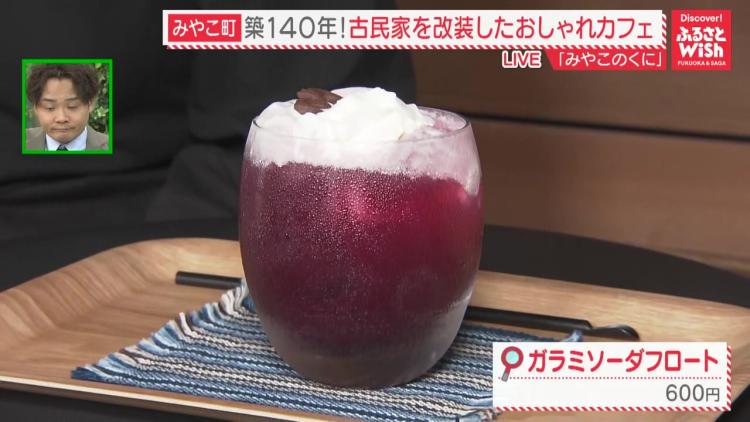小倉藩主の“書の師範”を務めるなど、幕末から明治時代に活躍した異才の書道家がいた。
みやこ町に自生する藤カズラを叩いてほぐした「かずら筆」を作り出し愛用したという。
1989年、地元の有志の手により約100年ぶりに「かずら筆」が復活した。
ここから「かずら筆」に興味を持ち、作り始めたのが塚田聰さんだ。

切り出したカズラを木槌で叩いて、繊維をほぐす作業は見た目ほど簡単なものではない。
力強く叩けばよいというわけではなく、毛(繊維)が切れないような力加減が必要だという。
毛の量は足りているか、固すぎないかなど見た目よりも筆として機能しているかを意識する。

筆の先がまとまらず、書いたとき、荒く、力強い線になるのが「かずら筆」の特徴。
自然のカズラを使用するため、筆自体も真っ直ぐではなく、一つとして同じ筆は出来ない。
人と同じようにそれぞれ個性が現れる。それが「かずら筆」の魅力だという。

そんな、塚田さんが未来に残したい風景は「八景山から見るみやこ町」
行橋市との境に位置していて、子どもの足でも簡単に登ることができる低山だ。
子どもたちが遠足で訪れるなど、地元の人々に親しまれている。

山頂にある護国神社の鳥居には董村の書が刻まれるなど、塚田さんにとっても馴染みある場所。
社の横には「八畳岩」と呼ばれる大きな一枚岩があり、子どもの頃は、よく登って景色を眺めたという。
今でもたまに足を運ぶことがあり、懐かしい気持ちとともに元気をもらえる大切な場所だ。
※この記事は2022年の情報です(「STORY」11月20日放送)。
GENRE RECOMMEND
同じジャンルのおすすめニュース
-
同じジャンルのおすすめニュースは見つかませんでした。
AREA RECOMMEND
近いエリアのおすすめニュース