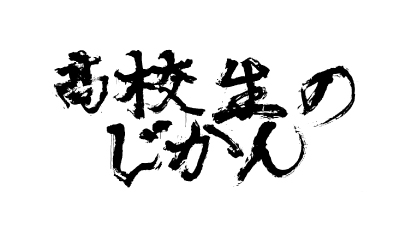「とびかんな」(福岡県朝倉郡東峰村)
2025年04月20日

「小石原焼」とは福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で作られる陶器のことで、そのはじまりは江戸時代初期と言われている。
今でも40以上の窯元が存在しており、陶器祭りでは多くの人が県内外から、自分の器や贈り物の器を探して集まってくる。
そんな小石原地区で、歴史とモダンを融合させた器を作っているのが、翁明窯元の鬼丸さんだ。

小石原焼の代表的な技法のひとつに「とびかんな」がある。
器の表面や側面にデザインされている畳目状の模様が特徴だ。
とびかんなとは、乾燥した陶器を高速で回転させ、そこにかんなの刃先を当てて、規則的に小さな削り目を入れていく技法なのだが、鬼丸さんが使っているかんなは、古時計のゼンマイを使用している。

古い柱時計に使用されていたゼンマイを鬼丸さんはオークションなどで取り寄せ、研磨して、自分の作品に適したかんなを自作している。
今は主に陶器を作ることが多い鬼丸さんだが、以前は磁器も作っていた。
その磁器に「とびかんな」を入れる際に、ゼンマイの硬さがちょうどよかったそうだ。
その流れで、今でもゼンマイをかんなとして使用しているという。
だが、器の硬さや角度、大きさで使用するかんなも違ってくるので、作品に応じたものを何種類も用意している。
失敗すると取り返しがつかない「とびかんな」。
技術と同様に、道具も重要だ。

そんな翁明窯元の鬼丸さんが未来に残したい風景は「小石原地区」だ。
小石原で生まれて、当然のように煙突のある町で育った。
まるで絵本のような世界で、のんびりとした美しい自然が今でも広がっている。散歩をすれば季節の花と出会い、四季の移ろいを楽しむ。
そして「とびかんな」で作ったマグカップでコーヒーを飲む。
それが鬼丸さんの癒やしであり、ライフスタイルなのだそうだ。